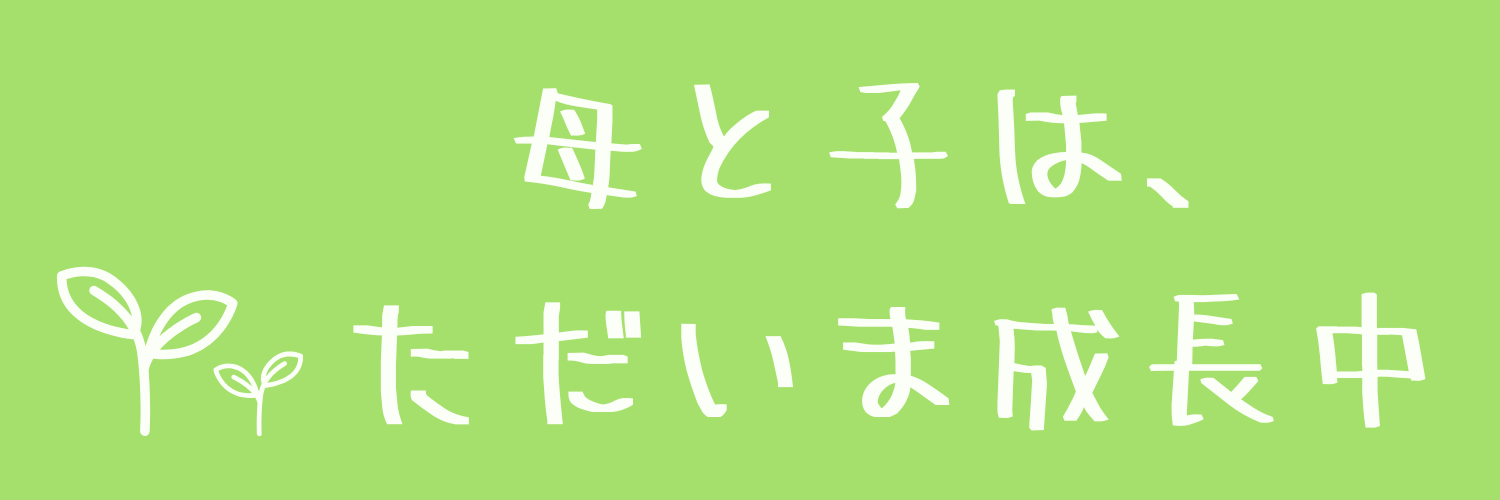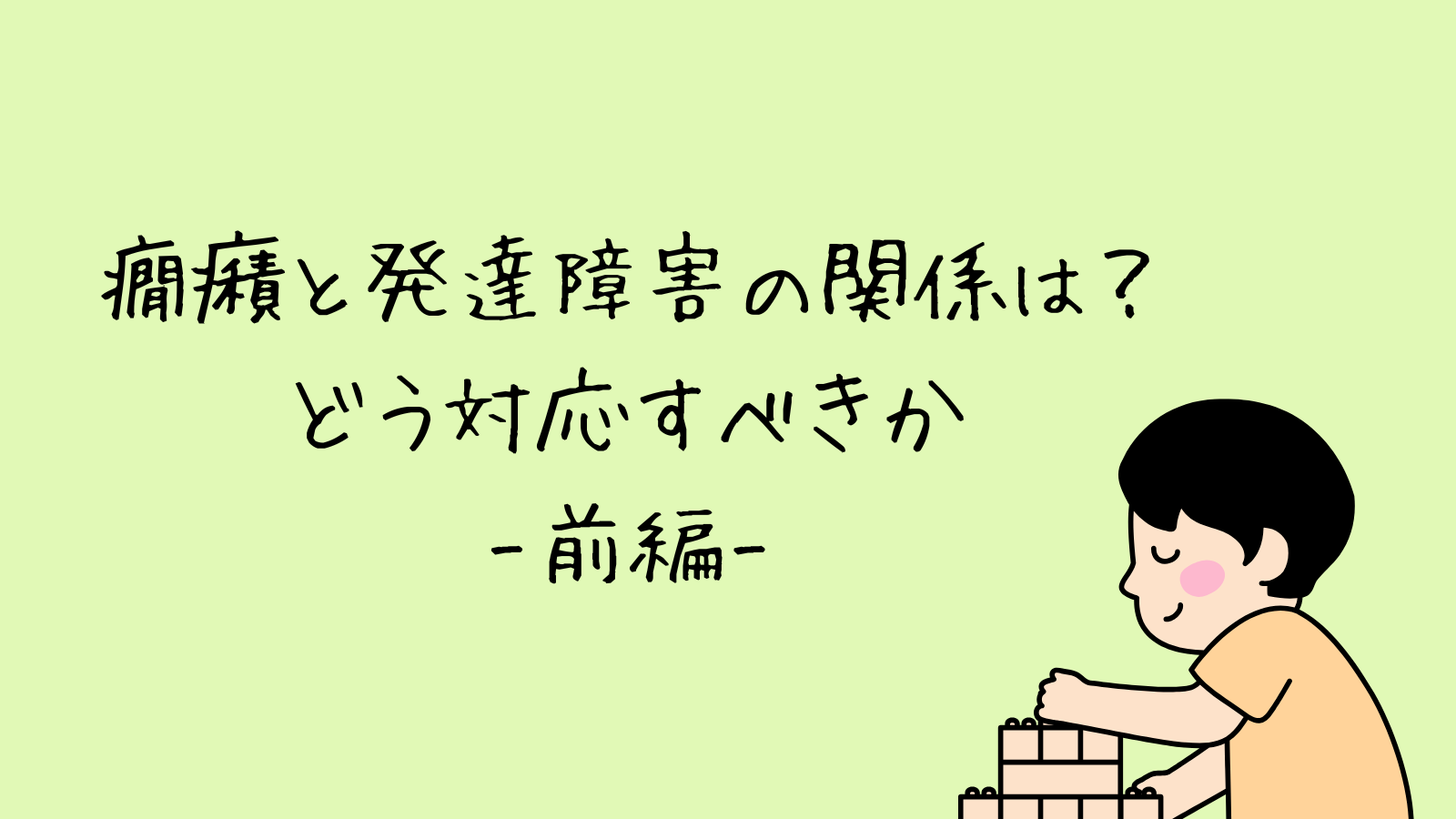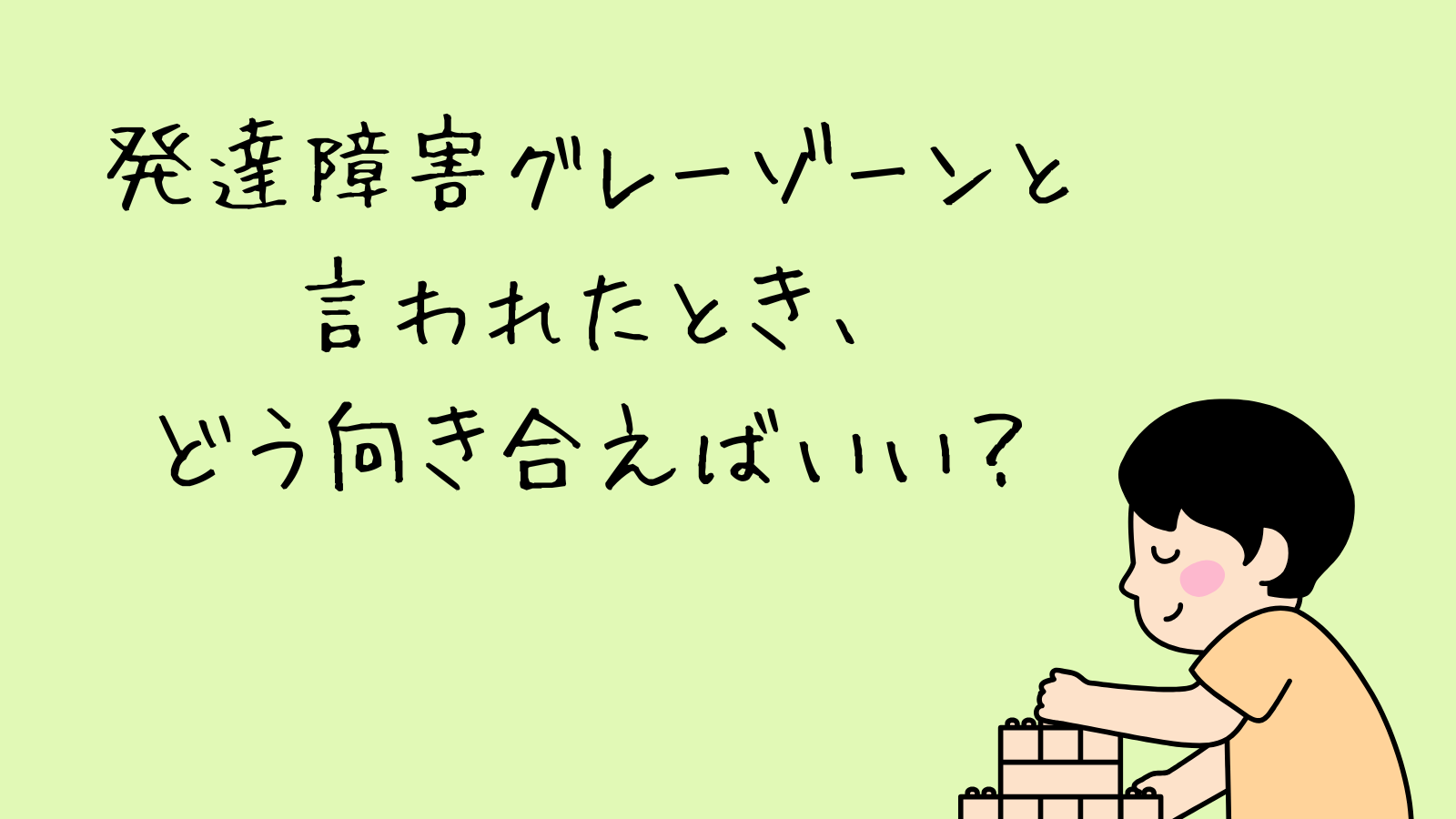癇癪と発達障害の関係は?どう対応すべきか-後編-
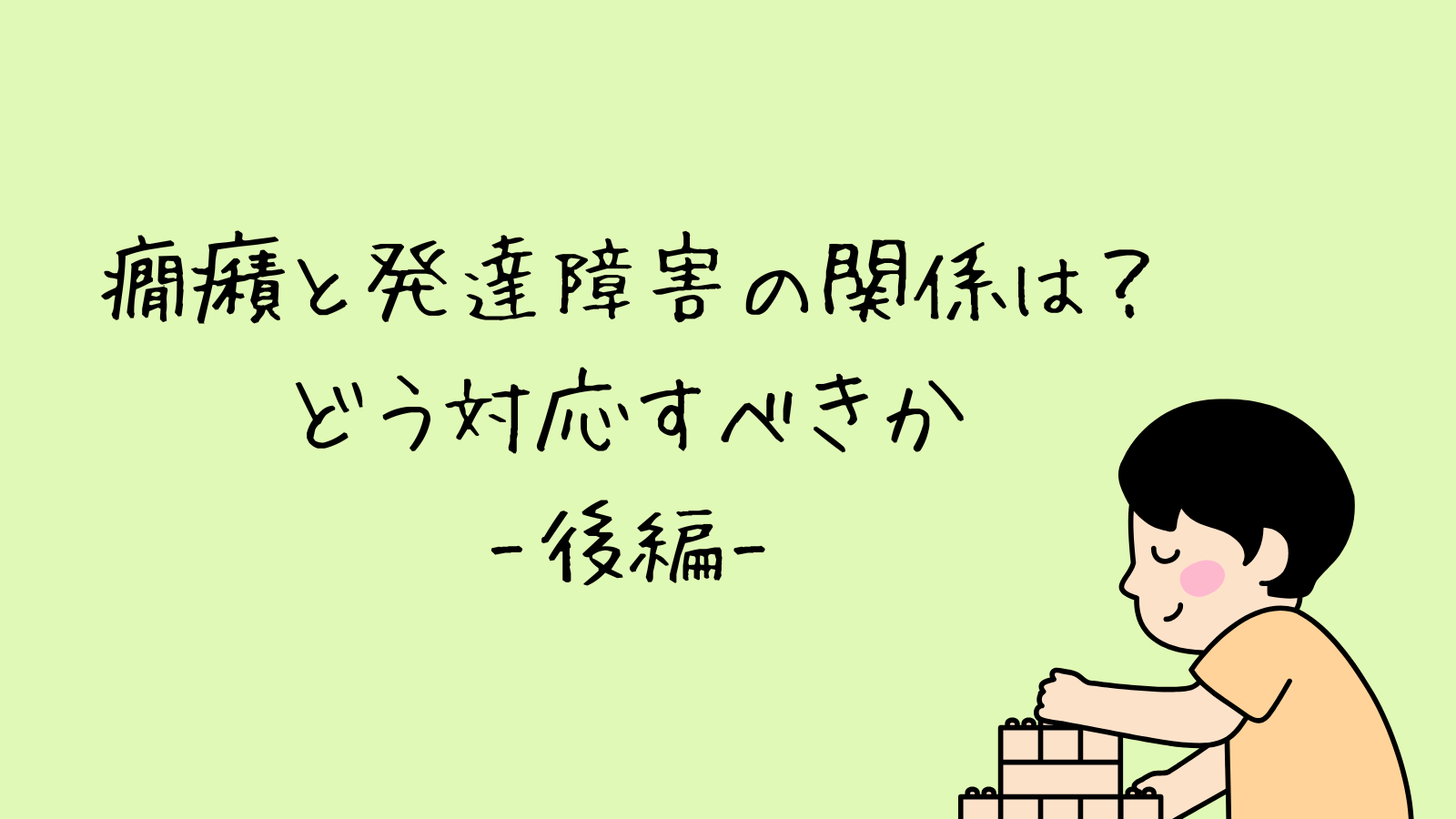
※この記事は前後編の【後編】です。前編では、私が息子の癇癪に気づいたきっかけや、日々どのような対応をしているのかをご紹介しました。
後編では、癇癪に悩む中で親として感じたことや、「自分を責めないための考え方」、そして相談先などをご紹介します。
「うちの子だけ?」「私が悪いの?」と悩んでいる方に、少しでも気持ちが軽くなるヒントを届けられたら嬉しいです。
前編はこちら↓
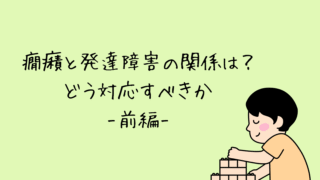
自分を責めなくていい
子どもの癇癪は大変ですが、うまく対応できないからといって自分を責める必要はありません。
親だって最初から完璧にできるわけではありません。
子どもが生まれて初めて親になるのですから、うまく対応できなくても当然です。
私も、息子の癇癪にどう対応すればいいのかわからず、何度も悩みました。
「もっと上手に対応できれば、こんなに暴れることはないのでは?」と自分を責めることもありました。
ただ、試行錯誤する中で気づきました。
「みんな初心者なのだから、うまくできなくて当たり前なんだ」と。
親も子どもと一緒に成長していくものです。
完璧でなくても大丈夫です。
しつけのせいではない
子どもの癇癪は、しつけの問題ではありません。
癇癪をおこす理由はさまざまで、「親の甘やかし」や「しつけの仕方」だけが原因ではないからです。
私も「自分が甘やかしてしまったから、すぐに癇癪を起こすのでは?」
「しつけが悪かったのだろうか?」と悩みました。
けれども情報を色々集めていくうちに、癇癪は成長の過程でよくあるもので、必ずしも親の育て方のせいではないとわかりました。
癇癪は子どもの成長の一部。
しつけのせいだと自分を責める必要はありません。
癇癪に対してイライラするのは当然
子どもの癇癪にイライラしてしまうのは当然です。
親だって人間です。
時間や気持ちに余裕がないときに、大声で泣かれたり暴れられたりすれば、誰でもイライラしてしまいます。
私も、「やらなければならないことが山積みなのに…」と焦りながら、息子の癇癪に対応していました。
どうしようもなくイライラして、「好きにしなさい」と怒ってしまったこともあります。
とはいえ冷静になって考えると、「イライラするのは仕方ない」と気づきました。
自分を責めても、余計にしんどくなるだけです。
「イライラしてしまうのは当たり前」と割り切れば、少し気持ちが楽になります。
少しずつ落ち着いてくる
癇癪は時間とともに少しずつ落ち着いていきます。
子どもは成長とともに、自分の気持ちを言葉で表現できるようになり、感情のコントロールも少しずつ上手くなるからです。
うちの息子は、4歳を過ぎても癇癪をおこしていました。
「本当に落ち着く日が来るの?」と不安でしたが、6歳を目前にして、毎日のようにあった癇癪が1週間に1~2回に減りました。
また、私自身も息子の癇癪に慣れ、少し冷静に対応できるようになったと感じます。
以前は大変だった癇癪対応も、気持ちの余裕を持てるようになりました。
癇癪はすぐにはなくならないかもしれませんが、確実に減っていきます。
焦らず見守っていきましょう。
不安なときは相談してみる
癇癪に悩んだときは、一人で抱え込まず相談するのが大切です。
専門家や周囲の人の意見を聞けば、新しい視点や対処法が見つかるかもしれません。
私は、「うちの子の癇癪がひどすぎるのでは?」と不安になり、小児科の先生や保健士さんに相談しました。
先生からは「発達障害でなくても、癇癪の激しい子はいますよ」と言われ、「そんなものかなぁ」と思いました。
発達相談窓口では、具体的な対応方法をアドバイスしてもらえました。
一人で悩まず、誰かに相談すると気持ちが楽になり、対応のヒントも得られるかもしれません。
幼稚園や保育園の先生
幼稚園や保育園の先生はいつもたくさんの子どもたちと接しているので、発達障害の特性がある子どもに気づきやすいでしょう。
先生から子どもの発達が気になる、と直接言われなくても、先生に家での気になる様子を話し、「園ではお友達とどんな様子ですか?」「先生たちが困っているところはありませんか?」と確認してみましょう。
小児科、児童精神科
病院では詳しく検査してもらえて、医師からアドバイスがもらえます。
「発達障害でなくても、この年齢でも癇癪の激しい子はいますよ」と言われれば、少しは安心できるかもしれません。
発達相談窓口
全都道府県に設置されている発達障害者支援センターでは専門知識の豊富な職員がいるため、具体的なアドバイスをもらえます。
発達障害の診断がなくても相談が可能です。
「癇癪がひどくて、どう対応すればいいかわかりません」と相談してみましょう。
その時に「どんな時に」「どのように暴れるか」を聞かれますので、具体的な状況エピソードをまとめておくといいでしょう。
いつか落ち着くときが来ると信じて、ただいま試行錯誤中!
うちの息子も、以前は癇癪をおこして1時間以上暴れました。
私も一緒に泣き疲れて、ぐったりしてしまいました。
「どう対応すればいいのか……」と考え、悩み、落ち込む日々。
それでも今振り返ると、少しずつ変化がありました。
2~3歳のころは毎日のように癇癪をおこしていたのが、6歳を目前にして週1回程度に減少。
行事の練習で疲れているときは癇癪をおこしやすいですが、それでも以前ほど頻繁ではありません。
「ひどい癇癪がずっと続くのでは?」と不安になる親御さんもいるでしょう。
でも、たぶん大丈夫です。
子どもは成長します。
感情をコントロールする力も、言葉で気持ちを伝える力も、少しずつ身についていきます。
他人を思いやる気持ちも育ち、以前なら癇癪をおこしていた場面でも、我慢できるようになります。
だから、お子さんを信じて、ゆっくり見守りましょう。