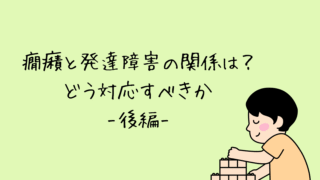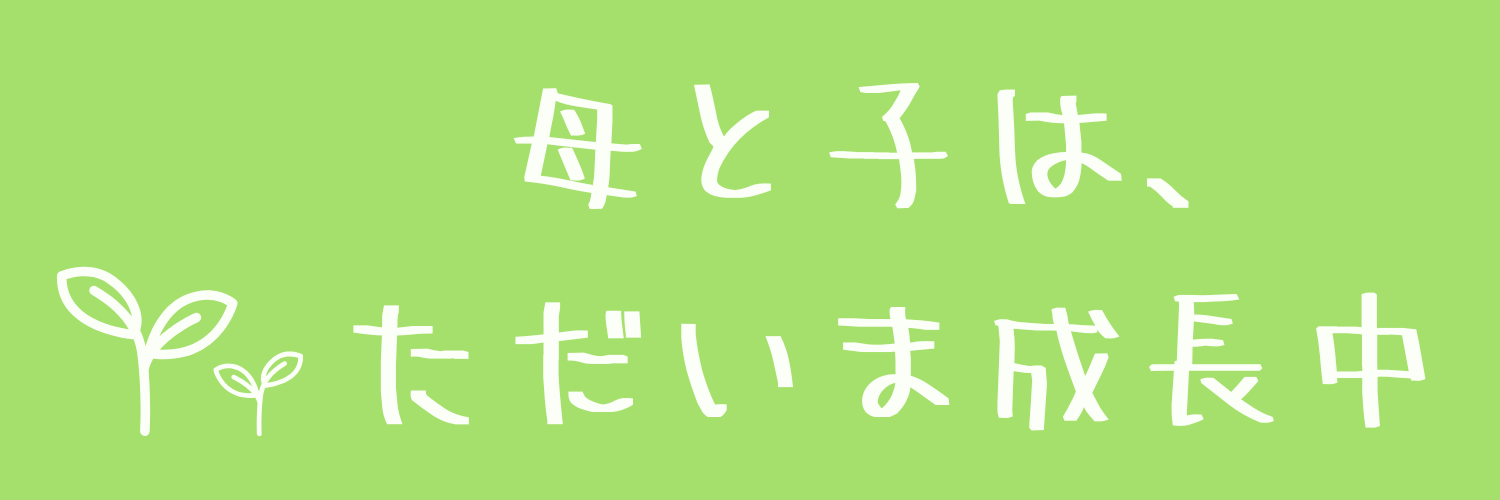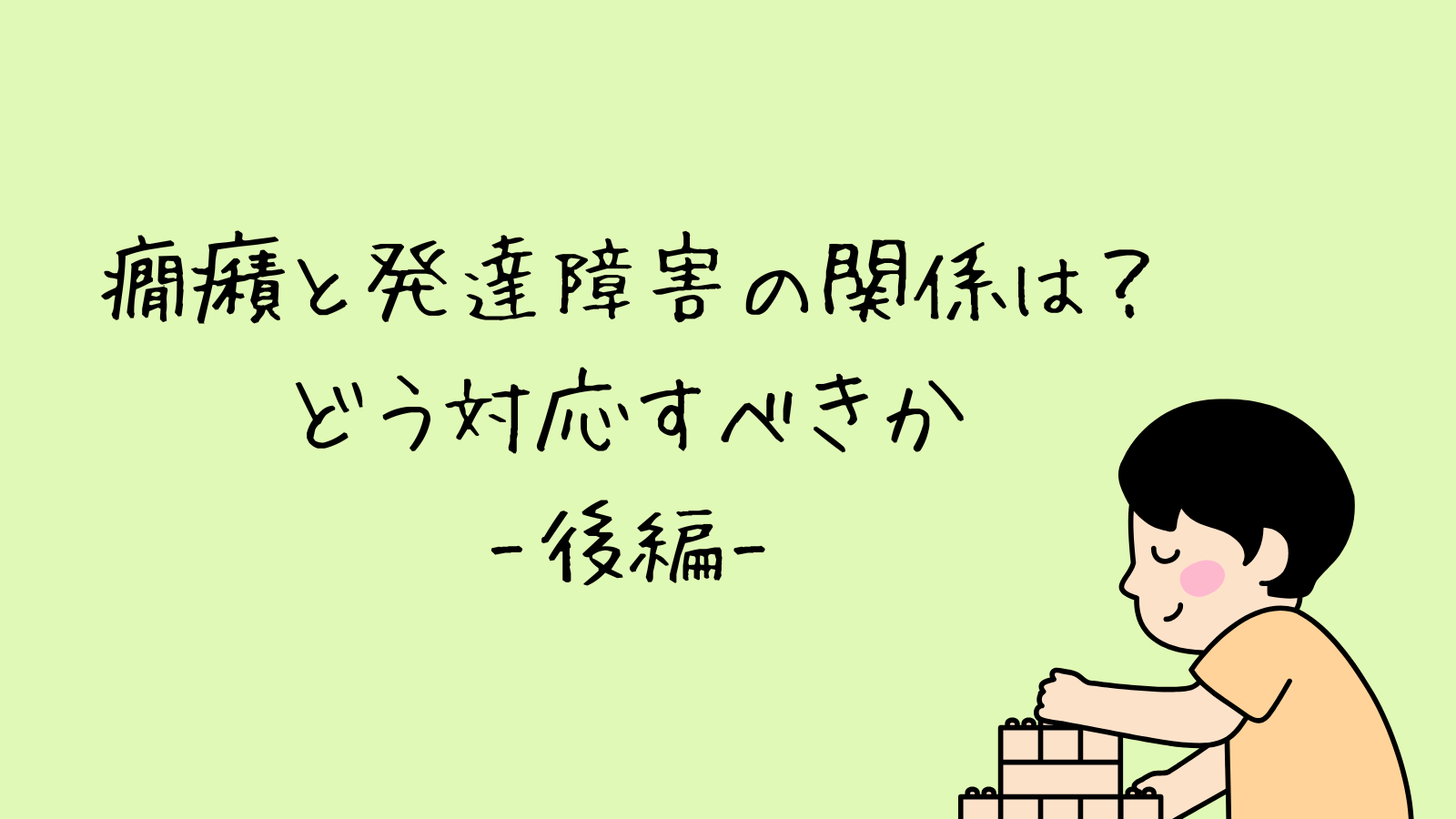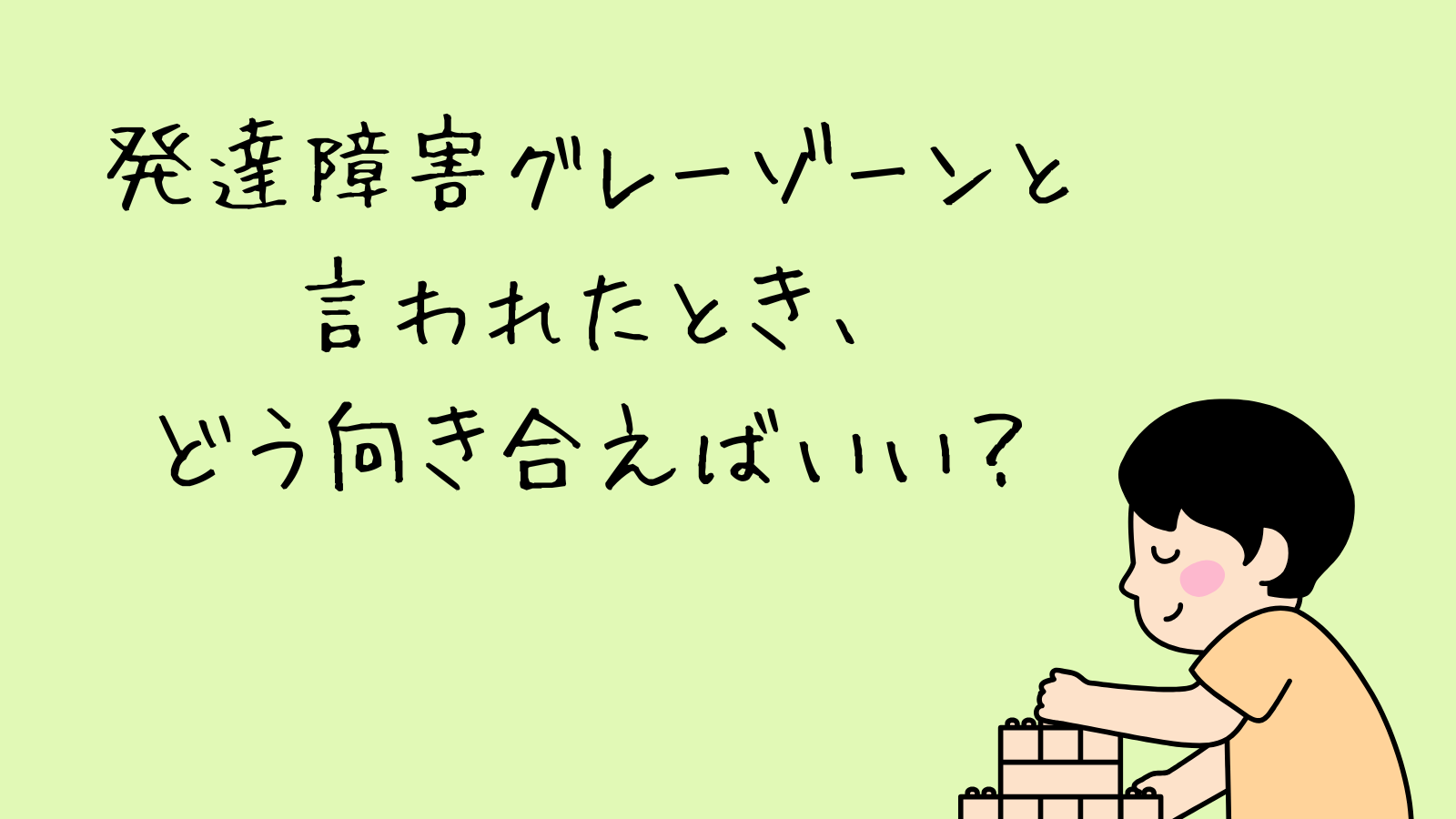癇癪と発達障害の関係は?どう対応すべきか-前編-
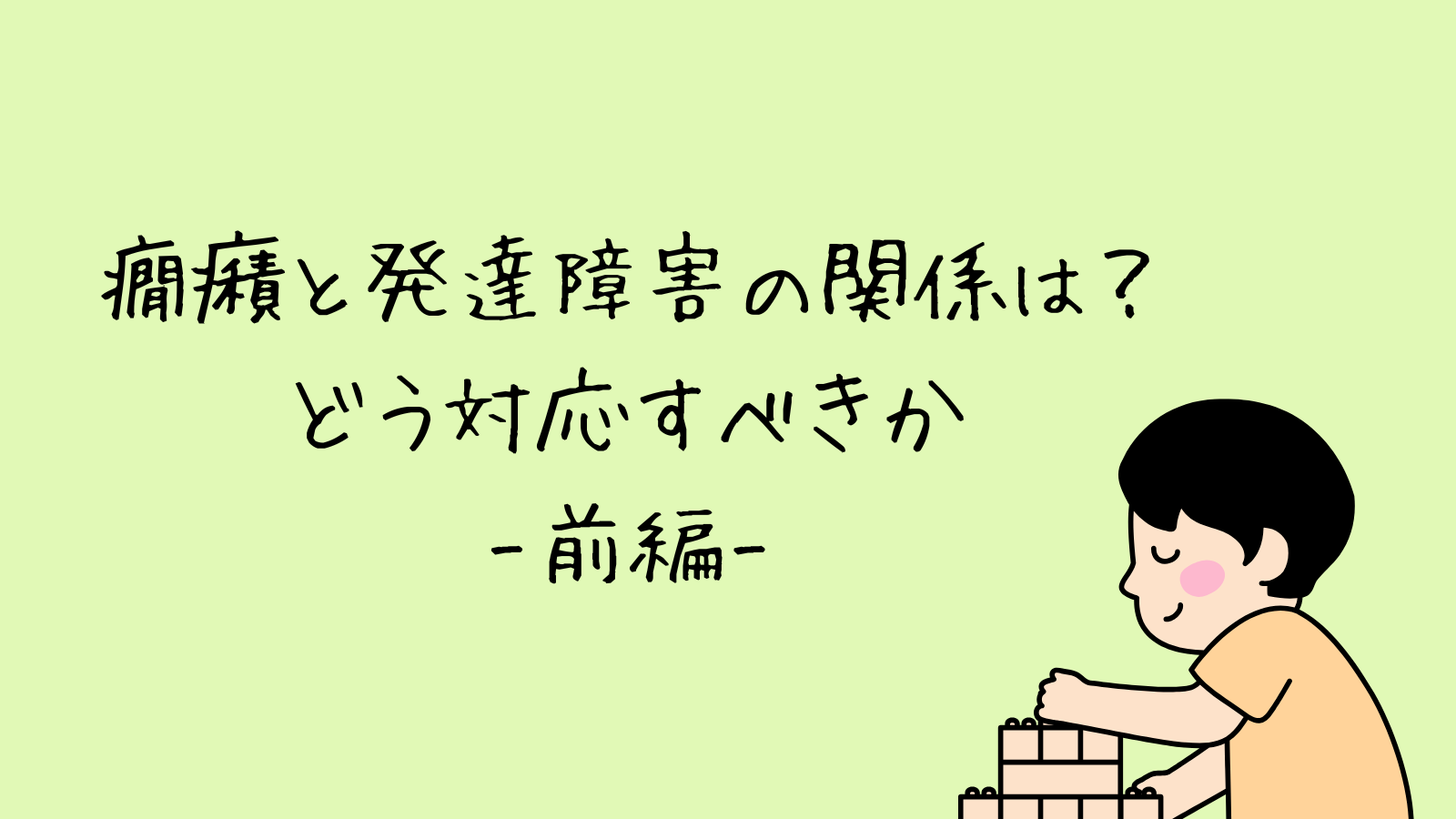
「癇癪がつらい」
「もう疲れた」
「いつ終わるのか」
「こんなに癇癪がひどいなんて、発達障害ではないか?」
どんな子どもにも癇癪はあると言われますが、あまりに頻繁だと「発達障害では?」と不安になりますよね。
確かに発達障害のある子どもは「こだわりが強い」「感覚過敏がある」などの特性から、癇癪をおこしやすいと言われています。
でも癇癪がひどいからといって必ずしも発達障害とは限りません。
私の息子は6歳になりますが、いまだに癇癪には手を焼いています。
いろいろな対処法を試しましたが、うまくいくこともあれば、まったく通用しないことも……。
それでも癇癪は成長とともに少しずつ落ち着いてきます。
うまく対応できないと感じても、どうか自分を責めないでください。
つらい日もありますが、試行錯誤しながら一緒に乗り越えていきましょう。
※この記事は前後編に分かれています。後編はこちら↓
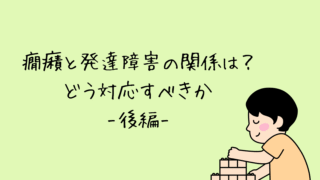
癇癪でもうヘトヘト!
うちの息子は2〜3歳の頃、毎日のように癇癪をおこして大暴れしていました。
子どもと一緒に泣きながら、どうすれば良いのかわからず私は疲れ切っていました。
毎日ワンオペで忙しいのに、癇癪の対応に時間がとられるのは本当につらいです。
散らかった部屋を片付ける元気もなく、やれなかったことは山積み状態……。
叫んで大泣き
うちの息子は癇癪をおこすと
「ママなんて大嫌い!」
「僕なんていないほうがいいんだ!」
と大声で叫びながら大泣きして暴れます。
以前アパートに住んでいたとき、ご近所から苦情が来てしまい、退去することになりました。
子どもを落ち着かせられず、ご近所の方にも迷惑をかけてしまい、本当に申し訳なく思います。
物を投げる
ひどい癇癪のときは、
・爪楊枝を床にぶちまける
・冷蔵庫に貼ってあるマグネットを全部はたき落とす
・おもちゃを投げて壊す
そんなことが日常茶飯事でした。
息子が落ち着いたあと、私は何度も泣きながら散らばったものを片付けました。
叩く、噛み付く
癇癪が激しくなると、息子は私を叩いたり蹴ったり、さらには噛みついたりします。
5歳になると力も強くなり、噛まれると本当に痛い…。
「もっと大きくなったら、今より暴れ方が激しくなるのでは?」と、不安でたまりませんでした。
周りの目も気になる
買い物中、息子がショッピングセンターの床に転がって泣いているのを知り合いに目撃され、「この前、お店で泣いてたね!」と言われたときは気まずかったです。
駅の改札前で転がって騒ぎ、警察官に声をかけられたこともあります。
お店の前で大泣きしていると、近所の方が「どうしたの?」と心配そうに出てくることも。
周りの視線が痛くて、何度も「もう外に出たくない」と思いました。
うまく対応できない自分を責めてしまう
息子が癇癪をおこすたび、私は「どうして自分はうまく対応できないんだろう」と落ち込みました。
「母親なら子どもを落ち着かせるべき」と思われているのでは?
「しつけがなっていない」と見られているのでは?
そんな不安ばかりが募り、息子が暴れるたびに自己嫌悪と罪悪感に押しつぶされそうになっていました。
発達障害なのではという不安
ほかの子どもの家での様子はわからないので、「もしかして、こんなに癇癪がひどいのはうちの子だけ?」といつも不安でした。
特に気になったのは信号機の赤。
赤信号を見るたびに怒って大暴れする息子を見て、
「こんな子、他に見たことない……」
と、ほかの子と比べて悩みました。
癇癪イコール発達障害ではない
「癇癪がひどい」こと自体は、発達障害の診断基準には含まれていません。
つまり癇癪がひどいから発達障害とは限らないのです。
私の息子は自閉症スペクトラム症のグレーゾーン ですが、担当医からは
「発達障害でなくても、この年代の子は癇癪がひどいことがありますよ」
と言われていました。
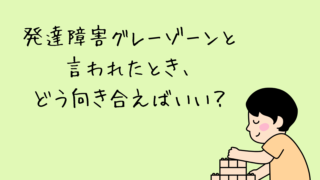
癇癪自体は成長の過程
発達障害がなくても癇癪をおこす子どもはたくさんいます。
「うちの子、癇癪がひどくて…」と、わざわざ言わないママも多いので、落ち着いて見える子どもだとしても、家では大暴れしているかもしれません。
癇癪の度合いは子どもによって違いますが、時間がたてばほとんどが落ち着くと言われています。
発達障害かどうかは病院で検査しないと分からない
発達障害かどうかは病院での検査と医師の診察を受けないと、はっきりわかりません。
ネットで発達障害の特性を調べて「うちの子、当てはまるかも?」と思っても、診断が確定するまでは自己判断できないのです。
癇癪対応
「子どもの癇癪にもっとうまく対応できれば……」と悩んでいる親も多いですよね。
うまく対応できて、子どもの癇癪がすぐに収まってくれればとても助かりますが、実際には難しく、1時間近く対応に追われることもあります。
癇癪の基本知識
子どもの癇癪は「わがまま」や「甘え」ではなく、未発達な脳の働きによるものです。
子どもは、自分の気持ちを言葉でうまく表現できません。
そのためイライラや不安、欲求不満を爆発させる形で発散させます。
特に2~3歳頃は自己主張が強くなる一方で、まだ感情をコントロールする力が未熟です。
この時期の癇癪は発達過程の一部だと言われています。
癇癪の原因
癇癪には、さまざまな原因があります。
子どもが何にストレスを感じているのか、を知るのが、癇癪対応の第一歩です。
自分の気持ちをうまく伝えられない
言葉がまだ発達していないと、「こうしたい」「こうしてほしい」が伝えられず、フラストレーションがたまります。
例:「ぶつけたところが痛いが、うまく言えない」→ 泣き叫んでしまう
感覚過敏
発達障害の特性のひとつとして、「音」「光」「肌ざわり」などに過敏な子どももいます。
例:「食べ物の触感がいつもと異なる」「雷の音が怖い」
こうした感覚のストレスも、癇癪につながる原因となります。
眠い、疲れている
大人でも寝不足や疲れているとイライラしますよね。
子どもはなおさら眠気や疲れで気持ちのコントロールが難しくなります。
例:「昼寝していなくて、夕方に大爆発!」
構ってほしい
「ママ、パパにもっと遊んでほしい!」
そんな気持ちが伝わらないと、注意を引くために癇癪をおこします。
例:「ママが料理していて、自分にかまってくれない!」→ わざと物を投げる
自分の思い通りにならない
「おもちゃが欲しい」「もっと遊びたい」など、自分の願いがかなわずに爆発……。
例:「お店でおもちゃを買ってもらえず、大泣きして床に転がる」
これは成長過程でよくあるので、「わがままだ」と決めつけないようにしましょう。
対応してみた結果
試行錯誤しながら、さまざまな方法を試してきました。
効果があったものもあれば、まったく通用しなかったものも…。
「この方法が絶対に正解!」というものはなく、子どもによって合う、合わないがあると感じました。
その時の状況や癇癪の原因によっても変わってきます。
私が試してみた癇癪の対応方法をご紹介します。
気持ちを代弁する
子どもの気持ちを代弁してあげると、癇癪が落ち着くと言われています。
子どもは自分の気持ちをうまく言葉で表現できなくて、イライラや悲しさが爆発してしまいます。
息子が癇癪をおこしたとき、「眠いんだよね」「うまくいかなくて悔しかったんだね」と、私が息子の気持ちを代わりに言葉にしてみました。
とはいえ気持ちを代弁したからといってすぐに癇癪が落ち着くわけではありません。
気持ちを代弁することは有効な場合もありますが、すべての子どもにすぐ効果があるわけではなく、根気強く試していく必要があります。
安全確保
子どもが癇癪を起こしたとき、まずは安全を確保するのが最優先です。
自分の頭を壁や床に打ちつけたり、物を投げたりしてケガする可能性があるためです。
息子が自分の頭を壁や床に打ちつけるとき、私はケガしないように手や足を押さえたり、抱きしめたりしました。
ただ癇癪を起こしているときに抑えられると、息子は「触らないで!」と余計にヒートアップしてしまいました。
2~3歳のころはまだ抑えられましたが、成長するにつれて力も強くなり、今は抑えきれる自信がありません。
安全確保は重要ですが、無理に抑えつけると逆効果になる場合もあるため、状況に応じて対応を考える必要があるでしょう。
見通しを持たせる
事前に予定を伝えておくと、癇癪を防げる場合があります。
突然の予定変更は、子どもにとって大きなストレスになり、癇癪の原因になりやすいからです。
息子は「自分はこうしたい」という思いが強く、予定変更には敏感です。
そのため朝や出かける前に「今日は〇〇と△△に出かけるよ」と伝えています。
ただ、予定が息子の希望と合わない場合は、外出前から癇癪をおこすことも。
「もうお出かけしない!」と暴れてしまい、予定がキャンセルになったこともあります。
予定を伝えることは有効ですが、必ずしも癇癪を防げるわけではなく、子どもの気持ちを考慮しながら柔軟に対応するのが大切です。
別なもので気をそらす
癇癪を回避するために、子どもの注意を別のものに向けるのが有効な場合があります。
癇癪がひどくなる前に気をそらせば、感情が爆発するのを防げるからです。
2~3歳のころは、「もうすぐテレビの時間だよ」「一緒に買い物に行こう!」と話しかけると、うまく気がそれて落ち着いてくれることがありました。
今でも、癇癪がひどくなる前なら気をそらせることもあります。
しかし、成長するにつれて「僕はそんなものに惑わされない!」と思うのか、別のことで気をそらすのが難しくなってきました。
幼いころは効果的でしたが、成長とともに気をそらすのが難しくなrりました。
そのため方法を工夫しなくてはなりません。
距離を置く
癇癪がひどいときは、一時的に距離を置くのが有効と言われています。
子どもが興奮状態にあるとき、すぐに落ち着かせようとすると逆効果になるケースがあるためです。
息子の担当医からは「癇癪をおこしたらトイレや別室に逃げ込んでください。しばらくすれば落ち着きます」と言われました。
わかってはいるものの、すがりつく息子を振りほどいて別室に逃げ込むのは至難の業です。
仮に別室に逃げ込んだとしても、壁や扉を叩く音が聞こえると、ケガしないか、物を壊さないかと心配になり、結局対応せざるを得ませんでした。
また、大声で泣き叫ぶため、近所から通報されるのではないかと気が気でありません。
距離を置くことが有効だとわかっていても、実際には難しい場面も多く、状況に応じた対応が必要だと感じました。
落ち着けたらほめる
癇癪をおこした後に落ち着けたら、「自分で落ち着けたね!」と褒めることが大切だと言われています。
子どもに「落ち着けた」と認識させると、自己肯定感を育てることにつながるためです。
息子の担当医に言われて、癇癪が収まった後に「自分で落ち着けて偉かったね!」と声をかけるようにしました。
それでも息子は相変わらず癇癪をおこし続け、劇的に変化があったわけではありませんでした。
自己肯定感は少し上がったのかもしれませんが、癇癪の原因があれば、またすぐ爆発してしまいました。
褒めるのは大切ですが、それだけで癇癪がなくなるわけではなく、長期的な視点で続けていくのが重要だと感じました。
効果があったり、なかったり
同じ方法でも、効くときと効かないときがあります。
「昨日はこれで落ち着いたのに、今日はダメだった…」
そんな日々の繰り返しですが、試行錯誤しながら進んでいくしかないと思います。
試行錯誤しながら成長中
毎日が手探りですが、少しずつ変化は見えてきます。
「前よりも落ち着くまでの時間が短くなったかも」
「一度は暴れたけど、自分で切り替えられるようになってきた」
そんな小さな成長を見つけるのが、親にとっても励みになります。
※この記事は前後編に分かれています。後編はこちら↓